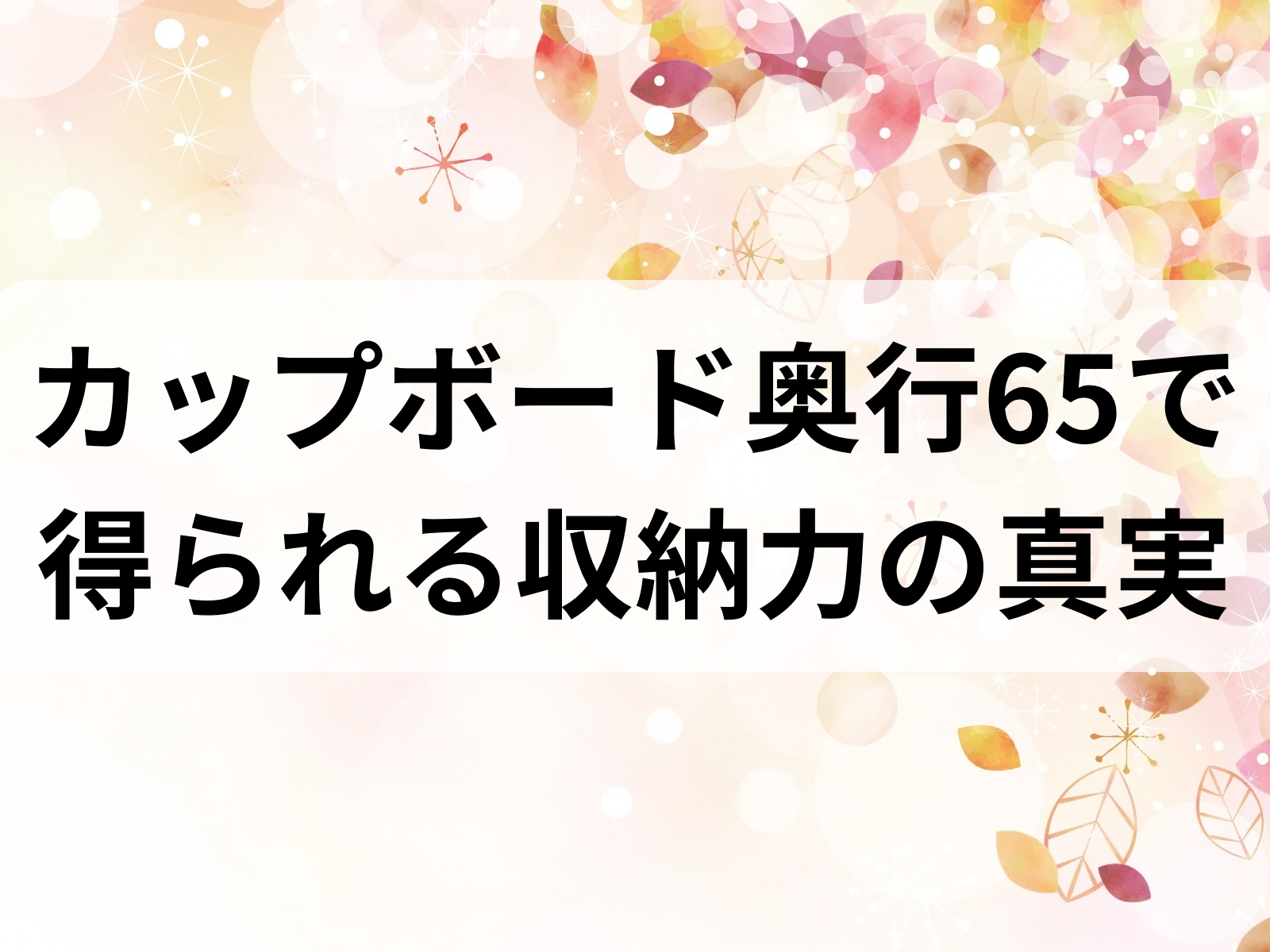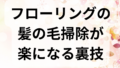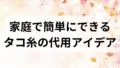キッチンの収納力や使い勝手を大きく左右するのが、毎日使う人にとって非常に重要なカップボードの奥行きです。
カップボードは、見た目の美しさだけでなく、料理や片付けの効率にも直結するキッチンの中核的存在。
その中でも「奥行65cm」は、使いやすさと収納力のバランスが取れたサイズとして、近年とくに注目を集めています。
従来の一般的な奥行きよりもわずかに深くなることで、大型の家電や深さのある調理器具、食品ストックなどもスムーズに収納可能になるという点が多くのユーザーから高評価を受けています。
また、見た目の統一感やキッチン全体のレイアウトにおいても、大きなアドバンテージを持っています。
この記事では、奥行65cmのカップボードがもたらす実用性・収納力・配置の工夫について、具体的な使用事例やレイアウトのヒント、選び方のポイントも交えながら、わかりやすく解説していきます。
カップボード奥行65の収納力の真実

カップボードの奥行き65cmとは?
カップボードの奥行65cmは、一般的なシステムキッチンのワークトップとほぼ同じサイズ感であり、見た目に統一感が出るだけでなく、機能面でも多くの利点があります。
たとえば、電子レンジや炊飯器といった大型のキッチン家電がスムーズに設置可能なうえ、カップボードの上に調理スペースとして物を置いたり、作業台として使ったりすることもできるため、利便性が飛躍的に向上します。
また、65cmというサイズは奥行60cmのモデルと比べてもわずか5cmの差ですが、その5cmが意外にも大きな差を生み出します。
たとえば、奥に物を収納しても手前のスペースに十分な余裕があるため、頻繁に使うアイテムの出し入れがしやすくなり、調理や片付けのストレスを軽減してくれます。
収納力はどう変わる?
奥行が広くなることで、奥行きのある家電や食器、食品ストックを余裕を持って収納可能になります。
特に収納スペースを2段、3段と縦に活用できるようになるため、上下の空間をフルに使える点も大きなメリットです。
引き出しの奥行も広がるため、背の高い瓶やボトル類、まとめ買いした調味料などもすっきり収まり、一目で中身を確認しやすく、出し入れもスムーズになります。
さらに、奥行に余裕があることで、用途別に仕切りや収納グッズを活用しやすくなり、整理整頓がしやすくなるのも魅力です。
奥行65cmのカップボードのメリット

スペースを有効活用する方法
奥行を活かして、上下に収納を分散させたり、壁面収納と組み合わせたりすることで、無駄のない空間設計が可能になります。
たとえば、カップボード上部には吊戸棚を設置し、日常的に使用しないストック品や季節限定の食器などを収納。
下部には引き出し式の収納を採用することで、取り出しやすく、視認性も高い実用的なスペースを実現できます。
また、奥行のあるスペースを活かして、スライド式の収納ラックや縦型ワゴンを組み込むことで、狭い空間でも多機能な収納力を確保できます。
さらに、収納だけでなく作業スペースとしても活用するために、天板部分を調理補助スペースとして利用するのもおすすめです。
キッチンとの動線を考慮したレイアウト
システムキッチンと同じ奥行なので、調理中の動線が自然に整うのが大きなメリットです。
シンクからコンロ、カップボードへと無駄のない流れが作れるため、食材を取り出す、下ごしらえをする、調理後に収納するという一連の作業が効率よく進みます。
また、冷蔵庫や電子レンジなどの大型家電との配置バランスも取りやすく、「一歩で届く」快適な動線設計が可能です。
小さなお子さんがいる家庭や、高齢の方が使うキッチンでも、スムーズで安全な動線が確保できます。
理想の配置事例と失敗事例
成功事例では、冷蔵庫との距離感やゴミ箱の配置まで計算されており、無理のない導線が確保されています。
さらに、コンセントの位置や照明の当たり具合まで考慮することで、使いやすさが格段にアップします。
調理家電をスライド棚に置くことで、蒸気や熱を安全に逃がしながら使える点も高評価です。
一方、失敗例としては、通路幅が狭くなり過ぎたケースや、扉の開閉スペースが確保できず、使い勝手が悪くなった例があります。
また、奥行があることで奥のものが見えづらくなり、結局使わなくなってしまうというパターンも見られます。こうしたリスクを防ぐためにも、実際の導線をイメージしたレイアウト設計と収納アイテムの工夫が欠かせません。
収納力を最大化するためのアイテム

引き出しやゴミ箱の配置の工夫
奥行きを活かした引き出し収納で、縦にも横にも空間をフル活用。
特に奥行65cmあることで、引き出しの内部も大容量化し、大皿や背の高い瓶類、保存容器などを無理なく収納できます。
さらに、仕切り板や収納ボックスを活用することで、ジャンルごとに整理整頓しやすくなり、取り出しもスムーズに。
また、ゴミ箱はカップボード内に収めることで、見た目もスッキリし、生活感を抑えられます。
蓋付きのスライド式ゴミ箱ユニットや、分別用の3連ワゴンなどを採用することで、キッチンの清潔感と機能性が格段に向上します。
家電スペースをどう確保するか
電子レンジや炊飯器などの家電スペースは、スライド棚やコンセント配置を工夫することで使いやすさがアップします。
たとえば、炊飯器や電気ポットは使用時に蒸気が出るため、スライド棚に設置することで引き出して使用でき、熱や湿気のこもりを防げます。
また、コンセントの数や位置も重要で、家電のコードが干渉しないようなレイアウトを意識することが大切です。
複数の家電を同時に使うことを想定して、電源の容量にも配慮した設計が求められます。
追加収納で満足度を上げる
キッチン上部や横に吊り戸棚やワゴンを追加することで、より多くのアイテムを収納でき、整理整頓がしやすくなります。
吊り戸棚には普段あまり使わない調理器具やストック食材をしまうと便利で、見た目のスッキリ感も保てます。
また、カップボード脇にスリムタイプのキャスター付きワゴンを配置すれば、調味料やラップなどの小物類を取り出しやすい位置にまとめることができます。
収納スペースを増やすだけでなく、キッチン全体の作業効率と快適性も向上します。
カップボードの奥行き比較

他の奥行き(60cm、45cm)との違い
60cmはややスリムで扱いやすく、45cmは省スペース向きで、特に一人暮らしやコンパクトなキッチンに向いています。
それぞれに利点がありますが、収納力や利便性を重視する場合、65cmはその中でも最大級の収納力を誇ります。
たとえば、60cmでは奥行きのある調理家電や保存容器の配置に制限が出ることがありますが、65cmなら奥行きの余裕によって大型の電子レンジや炊飯器もストレスなく設置可能です。
また、65cmの奥行きは収納スペースだけでなく、作業スペースとしての利用も想定できるため、物を置いても作業スペースが狭く感じにくいというメリットも。
さらに、奥行きが深くなることで引き出しの容量も増し、上下の仕切りや収納ボックスも有効に使えるため、細かい道具類や食品ストックを無駄なく整理することができます。
これにより、調理効率が上がり、片付けのストレスも軽減されます。
見た目にも重厚感があり、システムキッチンとの一体感を演出しやすいサイズであるため、デザイン性を重視したい人にもおすすめです。
サイズ別の収納力評価
- 45cm:最低限の収納に特化。主にコンパクトキッチンや1人暮らしに適したサイズで、カップや小皿、調味料類の収納には十分。ただし、大きめの鍋や家電は収まりきらない場合があり、収納の工夫が必要です。
- 60cm:バランス型。収納量と省スペース性のバランスが良く、2人〜3人の家庭に最適。多くの市販カップボードの標準的サイズで、使い勝手に優れるが、大型家電やまとめ買い食材の収納にはやや余裕がないことも。
- 65cm:大容量かつ実用的。ファミリー層にも対応できる大容量収納が可能で、炊飯器・電子レンジ・オーブンなどの家電を並列で設置できる余裕あり。引き出しも深く広いため、調理道具や日用品を効率的に整理整頓でき、利便性が格段に向上します。
用途に応じた選び方
限られたスペースなら45〜60cmがおすすめです。
特に一人暮らしや狭めのキッチンであれば、45cmでも十分に対応可能で、動線の確保や作業スペースの維持がしやすい点が魅力です。
60cmはバランスが良く、2〜3人の世帯にちょうど良いサイズで、扱いやすさと収納力のバランスが取れています。
一方、広めのキッチンには65cmを導入することで、利便性が格段に向上します。
65cmの奥行きがあることで、収納だけでなく作業スペースとしても活用できるほか、大型の調理家電を複数並べて置くことも可能です。
家族が多く調理回数が多い家庭や、ストック品・調理器具が多い場合には、65cmの奥行きがそのニーズをしっかりカバーしてくれます。
また、使いたい収納アイテムや家電の大きさ・量に合わせてサイズを選ぶという視点も重要です。
設置場所の周囲にゆとりがあるかどうかもチェックポイントとなります。
キッチン全体の動線やデザインとの調和を考慮しながら、自分のライフスタイルに合った奥行きを選ぶことが、快適なキッチンづくりへの第一歩です。
リフォーム時の注意点

シンクやコンロとの距離
奥行65cmにする際は、調理スペースや通路幅が確保できるかを事前にチェックすることが非常に重要です。
特に調理中はシンクで洗い物をしながらコンロで加熱作業を行うなど、同時進行が多くなるため、スムーズに動ける距離感の確保が欠かせません。
また、カップボードが近すぎると、コンロ前での動きが制限されたり、複数人で作業する場合にぶつかるリスクもあるため注意が必要です。
最低でも90cm程度の通路幅を確保できるように計画することで、調理中の快適さが大きく向上します。
さらに、ゴミ箱の配置や家電使用時の開閉動作なども考慮して、余裕のあるスペースづくりを心がけましょう。
ダイニングとの統一感を持たせる
キッチンとダイニングが近い場合、カラーや素材を統一することで空間に一体感が生まれます。
たとえば、カップボードの扉の色をダイニングテーブルや椅子と同じトーンに合わせたり、木目やマット系の質感を共通にすることで、視覚的に広く感じさせる効果もあります。
さらに、照明器具や壁面のアクセントを連動させることで、よりまとまりのある空間演出が可能になります。
統一感があることで生活動線にも自然さが生まれ、日常の動きがストレスなく行えるようになります。
失敗しないための事前計画
現場の寸法確認、配線・配管の位置、使用頻度の高いアイテムの確認を事前に行うことで、後悔のない選択が可能になります。
特に、電源や水道の位置が制限となるケースが多いため、リフォーム前に必ず施工業者と一緒に動線と設備のバランスを確認しましょう。
また、収納する予定の家電やアイテムをリストアップし、それらを実際に配置した際に使いやすいかどうかをシミュレーションすることも重要です。
模型や設計ソフトなどを使って事前に可視化する作業は、使い勝手を大きく左右します。
見た目のデザインだけでなく、日常使いに耐えうる実用性を重視した計画を立てることが、リフォーム成功のカギになります。
カップボードの購入時に考慮すべきポイント

使用頻度の高いアイテムの位置
よく使う食器や調味料は、目線〜腰の高さに配置すると取り出しやすくなります。
特に、毎日使うアイテムは無理なく手が届く場所に置くことで、料理や片付けのストレスを軽減できます。
たとえば、食器類は引き出しの上段や吊り戸棚の下段に、調味料はカウンター上や浅めの引き出しにまとめると便利です。
また、家族構成や使用頻度に応じて、朝食用のセットやお弁当グッズ、よく使う保存容器などを「使用シーンごとにゾーン分け」して収納することで、キッチン全体の動線がスムーズになります。
見せる収納と隠す収納を使い分けることで、デザイン性と実用性の両立も可能です。
オーブンレンジや炊飯器の配置
蒸気や熱を考慮し、専用スペースやスライド棚を活用することで、安全性と利便性が両立できます。
炊飯器や電気ポットなどは、調理中に頻繁に使うため、作業動線の中心に配置するのが理想的です。
スライド棚を採用することで、使用時だけ引き出して蒸気を逃がし、使い終わったらスッキリ収納することが可能です。
さらに、オーブンレンジは上に熱がこもらないように上部に十分な空間を確保する必要があります。
機種によっては放熱スペースの指定があるため、メーカー推奨の設置距離を守ることが重要です。
コンセントの位置も考慮し、配線が邪魔にならないよう工夫すると、より快適な調理環境が整います。
設置場所の広さを確保する
65cmの奥行きを選ぶ場合は、周囲に余裕のあるレイアウトを意識することで、使い勝手がさらに良くなります。
たとえば、カップボード前に90cm以上の通路を確保することで、複数人が同時にキッチンに立っても動きやすくなります。
扉や引き出しの開閉に必要なスペースも見落とせないポイントです。
また、家電の設置やゴミ箱の出し入れ、掃除のしやすさまでを含めて考えることで、日常的なストレスを最小限に抑えることができます。
余白のあるレイアウトは、見た目にも広がりを感じさせ、キッチン全体の印象を明るく開放的にしてくれます。
カップボードの実際の活用事例

1人暮らしの具体例
コンパクトな空間でも、調理家電や食器を無駄なく収納できる点が高評価です。
限られたスペースでも、カップボードの奥行65cmがあることで、電子レンジや電気ケトルなどの家電をしっかり置くことができ、作業台としても活用できます。
また、調味料や乾物、冷凍保存用のタッパーなどを種類ごとに分類し、引き出しや仕切りを使って整理することで、常にスッキリとした状態を保てます。
収納に加え、作業スペースも確保しやすいのがポイント。
カウンター上にちょっとした調理道具を広げる余裕があり、食材の下ごしらえも効率的にこなせます。
特に一人暮らしの場合、使用頻度の高いアイテムを集中配置することで、家事動線が短縮され、調理の時短にもつながります。
家族向けのプランニング事例
家族構成に合わせた収納ゾーンの分け方がカギです。
たとえば、家族4人のケースでは、1人ひとりの専用スペースを引き出しや棚ごとに確保し、誰がどこに何をしまうかを明確にしておくと整理整頓がラクになります。
お弁当グッズはまとめて1つのボックスに収納、子ども用の食器は低めの棚に配置して子ども自身で出し入れできるようにするなど、ライフスタイルに合わせた収納設計が好評です。
さらに、予備のストックや非常用の食品も分類して奥行きのある下段スペースに保管することで、収納効率と防災対策を両立する工夫も見られます。
効率的な収納を実現したケーススタディ
可動棚や引き出し、ワゴンを組み合わせたフレキシブルな収納で、散らかりがちなキッチンをスッキリ整頓できます。
たとえば、季節ごとに使用頻度の変わるアイテムを上段・下段に入れ替えることで、常にアクセスしやすい収納が保たれます。
また、キャスター付きのワゴンを取り入れることで、必要なときだけ手前に引き出せる移動式収納も実現可能。
限られたスペースの中でも機動力のある収納設計を取り入れることで、日々の生活の中でストレスを感じにくいキッチン環境が整います。
まとめ
カップボードの奥行65cmは、収納力・機能性・デザイン性すべてにおいて優れた選択肢です。
大容量の収納が確保できることで、食器類や家電、ストック食品などを効率よく整理できるだけでなく、調理や後片付けの際の動線もスムーズになり、日々のキッチン作業を快適にしてくれます。
また、システムキッチンとの一体感を持たせることで、キッチン全体の美観を向上させ、生活空間としての魅力も高まります。
収納だけでなく、作業スペースや見た目のバランスにも配慮することで、家族全員が使いやすいキッチンに仕上がります。
導入を検討する際は、ライフスタイルやキッチンの広さに合わせた配置とアイテム選びを意識し、自分にとって最適なレイアウトを模索しましょう。
この記事を参考に、後悔のないカップボード選びを進めてください。
設置後の満足度を高めるためにも、ショールームでの実物確認や、レビューの活用もおすすめです。