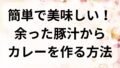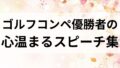体調を崩してしまうのは、どんなに気をつけていても誰にでも起こりうることです。特に季節の変わり目や寒暖差が激しい時期、または仕事やプライベートでの疲れがたまっているときには、1日ではなかなか体調が回復せず、やむを得ず2日連続で会社を休まなければならないこともあるでしょう。
そうしたとき、体調の心配に加えて、会社や取引先への連絡方法に悩む方も多いのではないでしょうか。「上司にどう伝えるべきか」「復帰の見込みをどう説明すればよいか」「相手に失礼のない文面とは?」など、不安や疑問が次々に浮かんでくるものです。
本記事では、体調不良で2日連続休む際に使える、実用的なメールの書き方と具体的な文例をわかりやすく紹介しています。社会人としての信頼を保ちながら、無理せず休養をとるために、ぜひ参考にしてください。
体調不良で2日連続休む際のメール文例

体調不良による連絡の基本
体調不良による欠勤連絡は、早めかつ簡潔に行うことが鉄則です。特に勤務開始前には必ず連絡を入れるようにし、連絡手段(メール・電話など)も会社のルールに沿って選びましょう。メールの場合は、読み手がスムーズに内容を把握できるよう、件名や冒頭の書き出しで要件を明確に伝えることが重要です。
また、連絡は単なる報告だけでなく、相手に与える印象を左右する「ビジネスマナーの一部」として捉え、丁寧な言葉遣いと配慮を意識することが信頼につながります。 体調が悪くて文章を考えるのが大変なときも、テンプレートを活用して最低限の内容はしっかり伝えましょう。
2日連続の欠勤の連絡方法
1日目に欠勤の連絡をした場合でも、2日目も別途メールを送るのがマナーです。前日と同じ内容を繰り返すだけではなく、「症状の経過」や「医師の診断があったかどうか」など、前日からの変化を一言添えると、相手に安心感を与えます。
また、体調の悪化によって復帰がいつになるか未定の場合は、「●日頃に再度ご連絡いたします」といった形で今後の対応を明示すると丁寧です。
メールの件名の重要性
件名には、「【欠勤連絡】氏名+本日もお休みします」など、要件がすぐに伝わる表現を使うようにしましょう。読み手が大量のメールの中でもすぐに確認できるよう、「欠勤連絡」「体調不良」などのキーワードを含めた具体的な表現がベストです。
例えば:
- 【欠勤連絡】○○(氏名)本日も体調不良のためお休みします
- 【ご連絡】○○(氏名)体調不良による連続欠勤について
受け取った側の立場に立って、スムーズな情報伝達を意識した件名づくりを心がけましょう。
必要な情報の明記と注意点
以下の情報は、過不足なく網羅することが求められます:
- 休む理由(簡潔かつ具体的に「発熱」「頭痛」などを含めると親切)
- 休む日付と連続であることの明記(「昨日に引き続き」など)
- 引き継ぎがある場合の担当者名や方法(「○○さんに業務共有済み」など)
- 回復の見通し(「明日の朝、再度体調を見てご連絡します」など)
過剰に心配させる必要はありませんが、安心して業務を任せられるように、誠意と配慮をもって伝えることが大切です。
具体的なメール例文集
上司への例文
件名:【欠勤連絡】○○(氏名)本日もお休みいたします
本文: ○○部長 お疲れ様です。○○です。
昨日より体調不良のため欠勤しておりますが、本日も症状が改善せず、お休みをいただきたくご連絡いたしました。熱は少し下がったものの、頭痛と倦怠感が続いており、無理に出社するとかえって職場にご迷惑をおかけしてしまう可能性があると判断いたしました。
業務については、事前に○○さんへ共有し、対応をお願いしております。緊急の対応が必要な案件がありましたら、○○さんを通じてご連絡いただけますと幸いです。
ご多忙の折、ご迷惑をおかけし大変申し訳ありませんが、体調の回復に努めてまいりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
同僚への例文
件名:【業務連絡】本日の不在について
本文: お疲れさまです、○○です。
昨日に引き続き、体調不良のため本日もお休みをいただいております。昨日は発熱があったのですが、今日は喉の痛みも加わり、病院での診察を受けて静養するよう指示されました。
急ぎの対応が必要な件については、○○さんにお願いしていますが、もしフォローが必要な点があればメッセージなどでお知らせください。
本日もご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
取引先への例文
件名:【ご連絡】本日の担当について
本文: ○○株式会社 ○○様 いつもお世話になっております。○○株式会社の○○です。
体調不良のため、昨日に続き本日も業務をお休みさせていただいております。回復の兆しはあるものの、医師より安静が必要との診断を受けておりますため、本日は引き続き同僚の○○が対応させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、引き続き○○をご指名いただけますよう、お願い申し上げます。復帰次第、改めてご連絡差し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。
復帰の連絡メール例
件名:【復帰のご連絡】○○です(出社再開)
本文: ○○部長 お疲れさまです、○○です。
体調が回復いたしましたので、本日より通常通り出社させていただきます。ご心配をおかけし申し訳ございませんでした。
休暇中は、業務のフォローなど多大なるご配慮をいただき、誠にありがとうございました。今後は体調管理により一層注意を払い、業務に励んでまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
連絡のタイミングとマナー
体調不良時のタイミング
連絡は始業の1時間前を目安に入れるのが基本的なマナーです。これは、業務開始直前や開始後に連絡するのでは、上司や同僚がその日の業務計画を立てづらくなり、チーム全体に迷惑がかかる可能性があるためです。特に業務の引き継ぎや調整が必要な場合は、できるだけ早めの連絡が理想的です。
また、緊急時に備えて、自分が所属する部署の連絡体制を把握しておくことも重要です。メールやチャットだけでなく、電話での連絡が推奨されるケースもあるため、連絡先はあらかじめスマートフォンに登録しておくと安心です。会社によっては、直属の上司だけでなく、チーム全体や人事部門への一斉連絡が求められることもあるため、就業規則や社内マニュアルの確認を事前に行っておくとよいでしょう。
注意すべきマナーとは
- 簡潔で明確な文章にする(長すぎず、要点を押さえる)
- 相手への配慮を忘れない(「ご迷惑をおかけしますが」などの表現)
- 謝罪とお礼の言葉を忘れない(「申し訳ございません」「よろしくお願いいたします」など)
- 無理に詳細な体調説明はしない(「発熱のため」など簡単な説明にとどめる)
これらを意識することで、ビジネスマナーを守りながら誠実な印象を与えることができます。
影響を最小限にする方法
事前に業務の引き継ぎ体制を整えておくことが重要です。日頃から、業務の内容や進捗状況を上司やチームメンバーと共有しておくことで、急な休みでもスムーズな対応が可能になります。
また、プロジェクト管理ツールや共有フォルダを活用して、自分が担当しているタスクやファイルの所在を明確にしておくことも大切です。さらに、代理で対応してもらう可能性のある同僚には、普段から感謝の気持ちを伝えておくことで、いざという時にも協力してもらいやすくなります。
体調不良に伴う業務の引き継ぎ
引き継ぎ内容の記載方法
引き継ぎ内容は、箇条書きで分かりやすく明記するのがポイントです。誰が読んでもすぐに理解できるよう、専門用語はなるべく避けて、簡潔で明瞭な表現を心がけましょう。また、タスクごとに「対応の優先度」「現在の進捗」「次に行うべき作業」などを整理しておくと、引き継ぎを受ける側もスムーズに対応できます。
さらに、業務に必要な資料や関連するファイルの場所、過去のやり取りの履歴(メール・チャットなど)も明記しておくと、背景を把握しやすくなります。引き継ぎ文書は紙だけでなく、共有フォルダやオンラインドキュメントにまとめておくと、後から確認できて便利です。
業務管理の重要性
日頃から業務内容を整理しておくことで、いざというときにもスムーズな対応が可能になります。担当している業務を「見える化」しておくことで、他のメンバーも状況を把握しやすくなり、突然の休みにも柔軟に対応できる体制が整います。
定期的に自分の業務内容を棚卸しし、やっていることをリスト化しておくと、休む必要が出たときにも慌てず対応できます。ToDoリストやタスク管理ツールを活用し、進捗状況を常に更新しておくことが望ましいです。
支障をきたさないための計画
- 担当案件の進捗をチーム内で共有(定例会やチャットでのこまめな報告)
- 緊急連絡先の明記(社内・社外問わず、関係者の連絡先一覧を作成)
- 代理対応者の事前確認(誰が何を代わりに対応できるかを明確に)
- 万が一のための備え(マニュアルや業務フローを文書化しておく)
- 体調不良時の社内ルールを理解・共有(事前に就業規則や休暇制度を確認)
体調不良からの復帰手続き
復帰前の準備
会社の就業規則に従い、必要であれば診断書の準備や上司への報告を行うようにしましょう。復帰前には、上司に対して現状の体調や復帰可能な見込みを伝えることが大切です。また、職場によっては復帰前の事前面談や健康状態の申告が必要となる場合もあります。社内規定や職場の慣習を確認したうえで、復帰までのスケジュールや必要書類の確認をしておくと安心です。
さらに、体調が万全であるかを自分自身でも見極めることが重要です。無理に復帰して再度体調を崩すことがないよう、余裕を持った判断を心がけましょう。
復帰時の連絡方法
感謝の気持ちを添えた連絡が大切です。「ご迷惑をおかけしました」と一言添えるだけで印象が大きく変わります。また、業務が滞らないよう、出社初日に何を優先すべきかを事前に確認しておくとスムーズな再スタートが切れます。必要であれば、引き継ぎ事項の再確認や、サポートいただいた同僚へのお礼の言葉も忘れずに伝えましょう。
復帰メールのタイミングは、出社当日の朝が基本ですが、前日のうちに伝えておくとより丁寧です。電話でのフォローを加えると、誠意が伝わりやすくなります。
必要に応じた診断書について
企業によっては2日以上の欠勤で診断書の提出が求められる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。提出が必要な場合は、病院での受診時にその旨を医師に伝えておくと、後日の再診を避けることができます。また、診断書の提出先や提出方法(手渡し・郵送・メール添付など)も職場ごとに異なるため、確認しておくことが大切です。
診断書の文面が必要なフォーマットであるか、記載内容が企業の基準を満たしているかも念のためチェックしておくと、提出後のトラブルを防げます。
その他の連絡手段の考慮
電話での連絡の仕方
急ぎの場合やメールが届かない可能性があるときは、電話での連絡が確実です。特に始業前の忙しい時間帯や、相手がメールを頻繁に確認しない可能性がある部署では、直接声で伝えることで、相手の理解度や反応も確認できるというメリットがあります。
まずは簡単にメールを入れておき、その後すぐに電話で要点を伝える方法が効果的です。メールで内容を残すことで記録にもなり、電話でのやり取りで不安や誤解を解消できます。また、電話をかける時間帯や相手の都合を考慮することも忘れずに。「今お時間よろしいでしょうか?」と一言添えるだけで、配慮ある印象を与えられます。
必要時の文書提出方法
診断書や欠勤届などの文書は、出社時に直接提出するか、PDFにしてメールで送るのが一般的です。体調不良で出社が難しい場合には、事前に上司へメールで提出の意向を伝え、可能であればスキャンや写真で撮影したものを添付する方法でも対応できる場合があります。
また、社内で定められた提出先やフォーマットがあるか確認し、不備のないように注意しましょう。診断書の場合は、医療機関に記載内容の指定があることも多いため、会社指定のフォーマットや記載事項があれば、あらかじめ病院に伝えておくとスムーズです。
無断欠勤のリスクと対策
無断欠勤は信用を大きく損なう行為です。 会社側にとっては業務が滞るリスクだけでなく、緊急事態でないかどうかの判断もできず、不安や混乱を招く原因になります。
どんなに体調が悪くても、一言の連絡は必ず入れましょう。もし動けないほどの状態であれば、家族やパートナーなど信頼できる第三者に代理連絡を依頼するのも一つの方法です。日頃から緊急時に備えた連絡体制を整えておくことが、自分自身と周囲の安心につながります。
まとめ
体調不良で2日間連続して休むことは、誰にでも起こり得ます。日々の仕事や生活の中で疲れが蓄積したり、予期せぬ体調不良に見舞われたりすることは、避けられないこともあります。そんなときに重要なのが、周囲への配慮と誠実な対応です。
欠勤時の連絡一つで、職場の信頼関係が維持できるかどうかが決まることもあります。上司や同僚、取引先に対して丁寧な連絡を心がけることで、誠意が伝わり、業務の混乱を最小限に抑えることができます。また、引き継ぎの準備や復帰の連絡、診断書の提出なども、会社のルールに沿って的確に対応することで、安心して職場復帰ができます。
この記事で紹介したポイントやメール文例を活用して、体調不良のときでもスムーズに欠勤・復帰対応ができるよう、日頃から体制を整えておくことも大切です。いざというときに慌てずに済むように、備えをしておきましょう。